
お城、お茶、そして怪談
ユニークな伝統・
文化が渦巻く水の都
日本屈指の大きさを誇る二つの湖、宍道湖(しんじこ)と中海、2つの湖をつなぐ大橋川、町のシンボル・松江城を囲むお堀、そして日本海。
さまざまな水辺の景観が楽しめることから“水の都”とも呼ばれる島根県松江市。
山陰地方最大の都市でありながら、松江城の城下町としての風情と、茶の湯などの伝統文化、そして怪談や民話が息づく希有な町でもあります。
岡山駅から特急「やくも」で約3時間半の道中は、忙しい日常から離れるのに十分かつ贅沢な時間。
非日常へとスイッチが切り替わったら、忘れかけていた日本の心を取り戻す旅の始まりです。

歴史・城下町
城とお堀と夕日と。一日中、違う感動に出会える町
松江市は大橋川にかかる橋を挟んで「橋北」「橋南」という二地区で構成され、「橋北」は城下町、「橋南」は商人の町として発展してきました。

「橋北」の中心は、“千鳥城”とも呼ばれる松江城。訪れたら最初に足を運びたいスポットですが、先に城の近くにある松江歴史館へ。町の仕組みや移り変わりを貴重な資料で紹介します。ここで知識を得ておくと、天守を見る目がガラっと変わります。例えばこの松江城、現存12天守かつ国宝指定5天守ですが、最上階の天狗の間は360度見渡せる望楼型となっています。現存天守なのでエレベーターはありませんが、急な階段を頑張って登ると美しい水の都を一望できます。

松江城からの眺望で殿様気分を味わった後は、遊覧船で堀川めぐりを。春は桜、夏は涼風、秋は紅葉、冬はこたつにあたりながらの雪景色、と四季折々の風情が楽しめます。

船を降りたら、武家屋敷が並ぶ「塩見縄手」や旧日銀のレトロ建築を改装した「カラコロ工房」などで「食」「買い物」「体験」を通じて松江を満喫しましょう。


日没前にはぜひ宍道湖畔へ。“夕日を見ながら散歩”という文化が根付くほど、松江の人たちと共にある宍道湖の夕日は、言葉にできないほどの美しさ。ちなみに湖畔に建つ島根県立美術館の閉館は夕日の見頃に合わせて、3月~9月は日没から30分後に設定されています。もしその日が曇りだったとしてもがっかりする事なかれ。雲に隠れた太陽が沈んだ瞬間、湖の色がピンクに変わる奇跡のような景色に出会えるかも。晴れても曇っても見ごたえ十分なスポットです。
橋をくぐるときに身をかがめなくてはならないのも一興。


茶文化
暮らしに根付いた、お気軽な茶の湯でリラックス
お茶の産地でもないのに、スーパーには抹茶がずらり。訪問客には、ポットのお湯で抹茶をシャカシャカ点てておもてなし。さらに食事の時は、小さな茶器で煎茶を飲むのがあたりまえ。煎茶を2杯以上飲むというルール以外、堅苦しい作法は一切なし。松江は日常に茶の湯文化が浸透している非常に珍しいエリアです。
その発端は松江の人たちが今でも「不昧公(ふまいこう)」と呼んで親しまれている松江藩松平家7代藩主の松平治郷公。17歳で藩主になり、財政を立て直した名君ながら、当代一の茶人としても名を馳せ、作法やしきたりにとらわれない茶の湯(不昧流)を広めました。松江は京都、金沢と並び、日本三大菓子処でもあり、不昧公が好んだ和菓子や茶道具は「不昧公好み」として今に受け継がれています。さらに松江は条例で不昧公の命日である 4月24日と毎月24日を「茶の湯の日」に制定。特別和菓子の販売やイベントなどが行われます。

そして、忘れてはならないのが「ぼてぼて茶」。農作業の合間に茶筅で泡立てた番茶に、煮染めや漬物を入れて一緒に食べたといわれる郷土料理です。これまた不味公が鷹狩りに出かけた際に飲んでいたものが由来なのだとか。茶の湯はハードルが高いと敬遠している人は、松江でお気軽なお茶を楽しんでみましょう。
不昧公。若い頃はやんちゃだったので、落ち着かせるためにお茶を習わされたのだそう。



怪談
小泉八雲が愛した松江は、「怪談」のふるさと
松江ゆかりの有名人といえば、「雪女」「耳なし芳一」などで知られる『怪談』の著者・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)。この地で暮らしたのはわずか1年3ヵ月ですが、昔ながらの文化や風習を色濃く残す松江は、彼が求めていた日本そのものだったよう。松江を「神々の国の首都」と呼ぶほどに愛し、ここで出会い結婚した妻・セツにこの地域に伝わる怪談を毎晩語らせていたそうです。
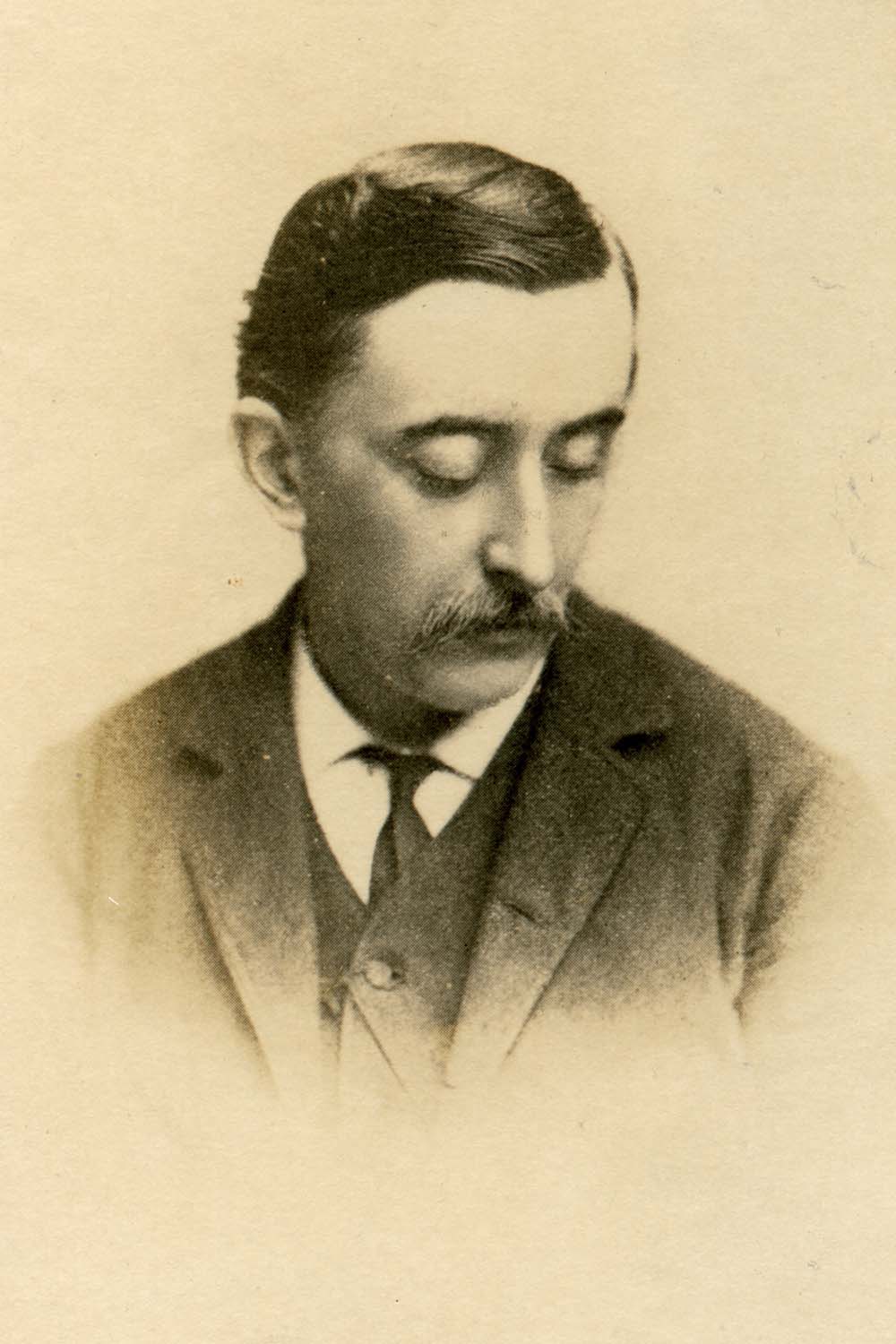
そんなわけで、松江は怪談のふるさとでもあります。城下町には、小泉八雲記念館や小泉八雲旧居が、さらに八雲が取り上げたさまざまな怪談の舞台が点在。これらを巡りながら、語り部による怪談を聴く「ゴーストツアー」はすべての開催日が満員になるほど大人気です。

余談ですが、昭和の中・後期に中学生だった人は、英語の教科書に「MUJINA」という話が掲載されていたのを覚えていませんか?(※地域によって教科書が違うので、該当しない方はごめんなさい) 実はこの「MUJINA」も小泉八雲が残した怪談の一つ。“Long, long ago(昔々)”と冒頭の一節をつぶやきつつ、若かりし日を思い出しながら、怪談のふるさとを歩いてみてはいかがでしょう。
八雲が愛した景観 シジミ漁・宍道湖の夕日

小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の妻・セツがモデルとなる主人公・松野トキを、髙石あかりさんが演じます。

グルメ
シジミにおそば、奥の深い「推しグルメ」に舌鼓
松江グルメの筆頭は、もちろん宍道湖のヤマトシジミ。宍道湖は海水と淡水が混ざり合う汽水湖で、松江市は漁獲量日本一を誇ります。そのヤマトシジミは粒が大きく肉厚。松江ではシジミ汁や酒蒸しだけでなく、佃煮、カレー、ラーメンなど、さすがご当地だけあって食べ方はバラエティ豊か。さらにシジミエキスを使用した地ビールまで登場するなど、シジミのポテンシャルの高さ、そして松江の人たちのシジミ愛の深さには驚かされるばかりです。また松江は出雲そば発祥の地と云われており、この地域を代表するグルメ「出雲そば」は、わんこそば(岩手県)、戸隠そば(長野県)と並ぶ日本三大そばの一つです。松江の人は誰もが自分の「推しそば店」を持っているほど、そば好きです。


そのほかにも、あご野焼きと呼ばれるトビウオのかまぼこやお茶文化に紐付いた不昧公好みの和菓子、小泉八雲が好きだったという羊羹など、多彩な味わいがずらり。最近、続々と登場している怪談をモチーフにしたスイーツは、味はもちろん、見た目の遊び心も抜群。お土産として喜ばれること請け合いです。
怪談スイーツ 怪談クッキー(アンボナール)、十六桜(三英堂)
当モールでも、松江産のシジミや地ビールをはじめ、さまざまなご当地商品がありますので、ぜひご覧ください。
ご紹介商品はこちら
記事の地域に関連した商品
あなたへのおすすめ記事
JR西日本では、地域の「いいとこ」「いいもの」を発信しております。
ご旅行・商品選びにぜひご活用ください。
-
 福岡 / 博多街に息づく歴史と文化 新たな魅力に出会える「博多」2025.03.31
福岡 / 博多街に息づく歴史と文化 新たな魅力に出会える「博多」2025.03.31 -
 和歌山 / 田辺熊野古道や山あいの名湯 豊かな海の幸にも心惹かれる2025.03.31
和歌山 / 田辺熊野古道や山あいの名湯 豊かな海の幸にも心惹かれる2025.03.31 -
 福井 / 三国・あわら北前船で栄えた湊町と福井県屈指の温泉郷を訪ねて2025.03.31
福井 / 三国・あわら北前船で栄えた湊町と福井県屈指の温泉郷を訪ねて2025.03.31 -
 岡山 / 備中高梁雲海の山城とジャパンレッドの町 伝統が息づく異世界へ2025.10.02
岡山 / 備中高梁雲海の山城とジャパンレッドの町 伝統が息づく異世界へ2025.10.02 -
 島根 / 松江お城、お茶、そして怪談 ユニークな伝統・文化が渦巻く水の都2025.10.29
島根 / 松江お城、お茶、そして怪談 ユニークな伝統・文化が渦巻く水の都2025.10.29 -
 大阪 / 枚方・交野歴史情緒あふれる枚方宿と七夕伝説のふるさとへ2025.10.29
大阪 / 枚方・交野歴史情緒あふれる枚方宿と七夕伝説のふるさとへ2025.10.29 -
 石川 / 能登豊かな里山里海に育まれた伝統文化と人情に触れる2025.11.18
石川 / 能登豊かな里山里海に育まれた伝統文化と人情に触れる2025.11.18 -
 福岡 / 小倉・門司歴史、夜景、レトロな街並み。楽しみ尽きない九州の玄関口2025.11.19
福岡 / 小倉・門司歴史、夜景、レトロな街並み。楽しみ尽きない九州の玄関口2025.11.19 -
 和歌山 / 紀南圧倒的な自然と神々が宿る聖地・紀南で規格外の体験を2025.12.10
和歌山 / 紀南圧倒的な自然と神々が宿る聖地・紀南で規格外の体験を2025.12.10 -
 鳥取 / 大山雄大な大山の懐に抱かれて 独自の歴史文化が息づく町々へ2026.01.06
鳥取 / 大山雄大な大山の懐に抱かれて 独自の歴史文化が息づく町々へ2026.01.06 -
 岡山 / せとうち波穏やかな海に育まれた「宝石」のような多島美の世界2026.01.08
岡山 / せとうち波穏やかな海に育まれた「宝石」のような多島美の世界2026.01.08







































